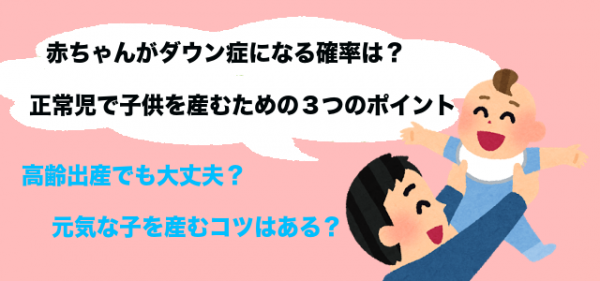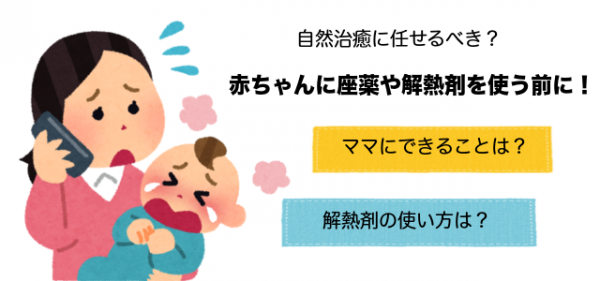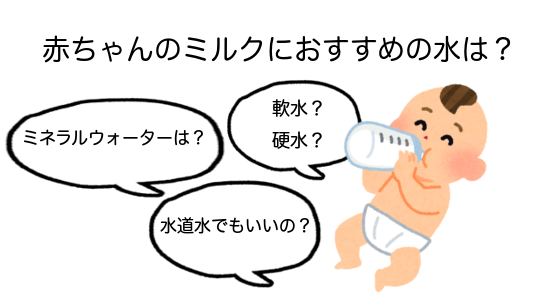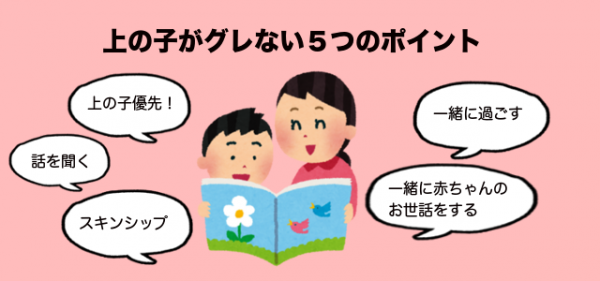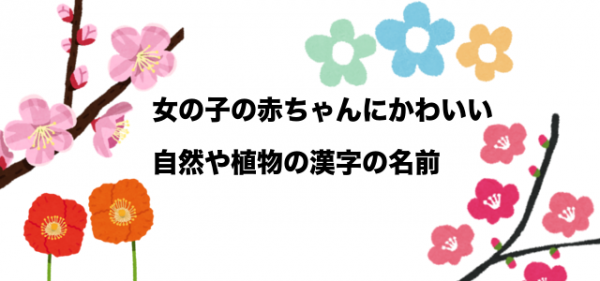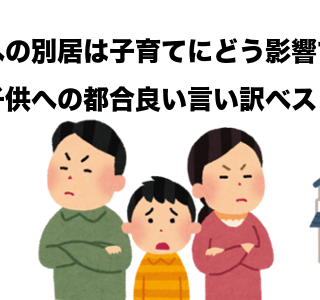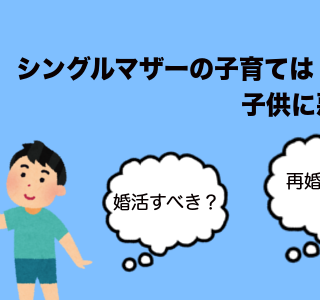結婚する前はラブラブだったのに、いざ結婚してみると価値観が合わない、性格があわないなどの不一致がでてきますよね。それががまんできるレベルであれば話し合いで解決できることもありますが、そうじゃないこともあります。
結婚する前はラブラブだったのに、いざ結婚してみると価値観が合わない、性格があわないなどの不一致がでてきますよね。それががまんできるレベルであれば話し合いで解決できることもありますが、そうじゃないこともあります。
他にも相手が浮気をしたり不倫をしたりして家族生活を営んでいくのが難しくなってしまったり、家にお金を入れない、家族の扶養義務を果たさないなど家族として生活していくのが難しいこともあります。
そうなってしまうと多くの家族が離婚へと向かっていきますよね。でも、子供がいる中での離婚は経済的にも不安だし、子供への影響も心配です。離婚すると子供にどんな影響があるのでしょうか?また、慰謝料や養育費って一体どれくらいもらえるものなのか気になるポイントをまとめてみました。
離婚の子供への影響は?
▼次のページへ▼